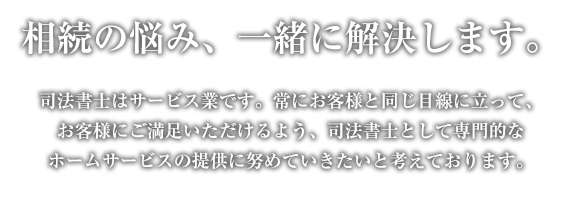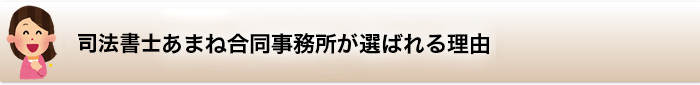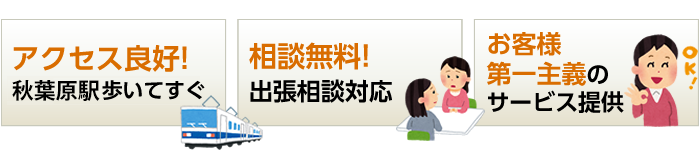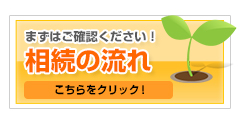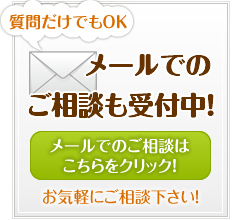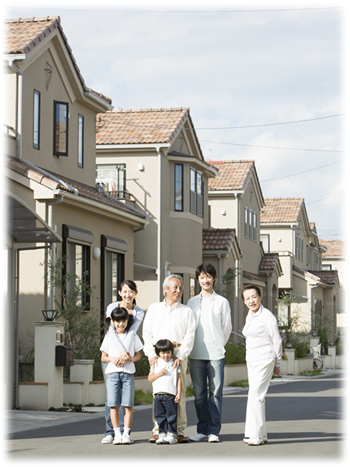
土地や建物を持っている人が亡くなった場合に、相続人となる配偶者や子供などに土地や建物の名義を変更する登記のことを「相続登記」と言います。
相続税の申告は相続開始後10ヶ月以内にしなければなりませんが、相続登記については、そのような期限はありません。
ただ、相続登記をしないことには相続人はその不動産の所有権を主張することはできませんし、もちろん処分することもできません。
また、相続登記をしないままの状態でさらに相続人が亡くなってしまうと、相続する権利のある人がどんどん増えてしまうため、遺産分割の協議が困難になってしまいますし、相続登記の際に必要な書類も増えて、登記手続きも大変になってしまいます。
このように、手続きが遅くなればなるほど面倒な問題が増えてきますので、相続登記はなるべく早く済ませることをお勧めします。
当司法書士事務所は、相続登記の専門家です。ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

遺言というと、「資産がそんなにあるわけではないから、あまり関係ない」、とか「死」というマイナスイメージが先行し、「ずっと歳をとって最期のときまでにすればいい」と考えられる方が多かったと思います。
ただ、最近では、雑誌やテレビ番組で相続や遺言、エンディングノートといったものが頻繁に特集されるようになり、以前より身近なものに変わってきているのではないでしょうか。
せっかく遺言書を書いても形式や内容に不備・漏れがあると、その遺言自体が無効になったり、または不完全なものとなって相続争いの原因となってしまうことがあります。
当司法書士事務所では、遺言書の作成サポートもアドバイスさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
中でも、以下に該当する方は、亡くなった後のトラブルを防ぐため、遺言を作成されることをお勧めいたします。
- 子供がいない
- 相続人が一人もいない
- 相続人の数か多い
- 内縁の妻(または夫)がいる
- 相続人の中に行方不明者がいる
- 障害を持つ子供に財産を残したい
- 家業を継ぐ子供がいる
- 不動産を所有している
- 再婚など、家族構成に複雑な事情がある
- 遺産を会社や福祉のために役立てたい
- 自分でもどのくらい遺産があるかよく分からない

司法書士はサービス業です。
常にお客様と同じ目線に立って、お客様にご満足いただけるよう、
司法書士としての専門的な法務サービスの提供に努めていきたいと考えております。
出張相談も可能です。ご相談は無料ですのでどうぞお気軽にご相談ください。
- 2013/09/05
- 【トピックス】婚外子の相続差別に違憲判決
- 2013/06/18
- 【相続】専門サイトをオープン致しました!
- 2012/05/15
- 遺言を無視することはできる?
- 2012/05/15
- 遺言に押印がされていない
- 2012/05/15
- 遺言を偽造した兄の相続権はどうなるか
- 2012/05/15
- 2通の遺言書